第25回『大転換期の中国の行方~「新皇帝X」の誤算と錯誤』
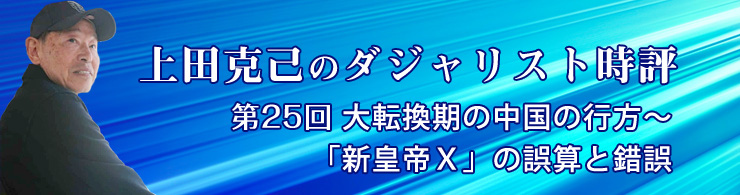
大転換期の中国の行方~「新皇帝X」の誤算と錯誤
米国と「世界の覇権」を競うまでに伸し上がって来た「大中国」が大きな転換期を迎えようとしている。昨年が創立100周年の中国共産党は今秋、5年に1度の党大会を開き、習近平(Xi Jinping シー・ジンピン)国家主席の「3期目続投」を決める。異例の政権長期化がスタートし、事実上の「新王朝・新皇帝」が誕生する。だが、前途には様々な「罠(わな)」があり、「覇権大国」への道は平坦ではない。
2022年は中国にとって歴史的な記念年。ニクソン米大統領訪中と日中国交正常化から50年、登小平が「改革開放」を促した「南巡講話」から30年、香港返還から25年、習近平の共産党総書記就任から10年など節目の年。「新皇帝」となる習近平は予てよりの「中国の夢」即ち「中華民族の偉大なる復興」を実現する決意を新にしている。ところが、「皇帝X」は少なくとも3つの「誤算」に見舞われ、3つの「錯誤」を犯しつつある。
第1の「誤算」は「経済成長の鈍化」。中国は2010年にGDP(国内総生産)が日本を抜き世界第2位の経済大国になった。それまでの30年間のGDPの平均成長率10.1%は、日本の「東洋の奇跡」、韓国の「漢江の奇跡」を上回る。さすがに、その後の5ヶ年計画は一桁台に落ちた。それでも日米欧に比べ成長率は高く、「共産党一党独裁」の「優位性」と「社会主義市場経済」の「有効性」を見せつけた。しかし、20年以降、成長率は3%台へ急落、回復を目指した今年も目標の「5.5%達成」は絶望的な見通し。
「成長鈍化」の原因は新型コロナ・パンデミックの発生と第2の「誤算」と言うべき「ゼロ・コロナ政策」の失敗が大きい。上海など厳しい都市の「ロックダウン」で経済活動が停止。更にウクライナ軍事侵攻のロシアを支持する中国に対し、欧米資本は中国からの撤退、対中貿易縮小へ向かった。そして高度成長の推進力だった「不動産バブル」が崩壊、非効率・不採算の「国有企業の残存」など「複合不況」に陥った。
一国の経済成長には「中所得国の罠(わな)」が潜む。ある程度、国民所得が向上すると、労働賃金などが上がり、それ以上の成長は難しくなる。中国はその「罠」にもはまった。
中国共産党にとって「経済成長」は広大な国土と多様な民族を「一党独裁」で統治する「最強のツール」。成長に伴う格差拡大などで不満、不平が生じても経済が成長、国民の生活が底上げされれば、共産党独裁の「正当性」は揺るがない。
中国のGDPが米国を抜き、「世界一の経済大国になる」のは時間の問題と見られていた。経済成長に急ブレーキが掛かり、「世界一の経済大国」の目標は遠退いてきた。
目下の中国経済はコロナなどによる「複合不況」だが、成長鈍化の根本原因は「人口減少」であり、日本と並ぶ「少子高齢化」の進行。1979年に始めた「1人っ子政策」が効いた。出生数の抑制、人口減少に伴い15歳から65歳までの「生産年齢人口」が2013年をピークに減り始めた。これに危機感を抱いた中国政府は「1人っ子政策」を緩和、21年には「3人っ子」へ拡大した。それでも進学率の向上、教育費の増加などの事情もあり、「少子化」に歯止めが掛かっていない。これでは「複合不況」は解消しても「成長鈍化の構造的要因」は消えない。
このため習近平は「国家主席の3期目就任」に当たり、党長老から「経済のV字回復」を条件付けられた、という。「1党独裁政治」と「市場経済」は矛盾した関係。この「偉大な矛盾国家」を習近平がどう操縦して「経済成長」という果実を再び手に出来るか。「偉大な実験」でもある。
第3の「誤算」は「一帯一路」戦略の行き詰まり。陸と海に「現代のシルクロード」を構築する壮大な「経済圏」構想は、習近平が国家主席に就任して間もなく打ち出した宿願のプロジェクト。米国と「世界の覇権」を争う上での重要戦略でもあった。
その参加国に離脱や開発計画の見直し、縮小が目立って来た。スリランカのように過大なインフラ投資で外貨不足に陥る「債務の罠」にはまる国が続出。ロシアの侵攻で「一帯」の欧州のゲートウェイだったウクライナに続きバルト3国など、「1帯」から離脱する国も相次いでいる。
習近平が対外拡大策の「一帯一路」に力を入れ、「戦狼外交」と言われる好戦的な姿勢を強めているのは、「国内の経済・社会の停滞」から「国民の目を反らせるため」との見方もある。米ジョンズ・ホプキンス大のルイ・ブランズ教授は、大国がリスクを厭わず、外に向かって無謀な行為に出るのは「衰退する大国の罠」と警告している。ロシアのウクライナ侵攻も同様だ。中国はロシアのウクライナ侵攻以降、ロシアとの関係を一層緊密化している。これが習近平の1つ目の「錯誤」。
いくら米国と経済面で競合し、貿易摩擦が起き、新疆ウイグルの人権問題で対立しても、ウクライナ侵攻の「ロシア支持」ほど西側自由主義陣営の「反発を買う判断」はなかった。米欧日などと中ロのデカップリング(分断)は決定的。「新しい冷戦」時代の幕開けだ。「一帯一路」は「債務の罠」にはまった国々と中国と連携強化のロシアが残るだけの「不毛帯一露」に成り果てようとしている。
2つ目の「錯誤」は香港の「1国2制度」の形骸化。香港は1997年7月に155年ぶりに英国から中国へ返還され、「1国2制度」がスタートした。中国は英国と「高度な自治」など「50年不変」の約束だった。
ところが習近平が国家主席に就任してから香港の民主派勢力を排除する動きを強め、これに反対する若者・市民のデモが活発化、大規模化した。すると中国・香港政府は20年に「香港国家安全維持法(国安法)」を施行、市民やメディアの自由で民主的な活動を抑え込んだ。
香港は中国返還後も20年間近く「世界で最も自由な経済体」と米シンクタンクから評価され、ロンドン、ニューヨークに次ぐ「国際金融センター」として機能、ニューヨークに次ぐ「富豪の多い豊かな街」だった。
そうした状況を保証した「1国2制度」が約束の半分の期間で骨抜きにされ、実質「1国1制度」化した。5年前に香港の10年後をパロディ化したオムニバス映画「十年」を観た。強権政治でディストピア(反理想郷、暗黒世界)と化した香港の姿が描かれた。それが10年後ではなく、5年後の今、現実化しようとしている。
25年前、香港の中国返還が迫ると、香港を脱出、他国への移住者は約30万人に上ったが、その後、約14万人が戻った。国安法施行に不安を感じ、今年6月末までの1年間に香港からの流出者は約11万人、人口減少数は12万人、減少率1.6%と過去最大を記録した。今年は経済成長はゼロの予測。中国政府にとっても大きな損失だ。
それ以上に習近平にとって痛いのは香港の「1国2制度の変容」が台湾に「強い警戒感を与えた」ことだ。もともと「1国2制度」は、中国が台湾の「平和的統一」のために考え出した「仕組み」。「香港の2の舞い」を嫌う蔡英文と台湾人の「独立意識」は強まり、中国本土と台湾の緊張関係は高まっている。世界に誇るべき「自由都市香港」の消滅は、国際社会へ中国に対する「不信感、失望感」を与えた。中国は寛大で多様性を包含した懐の深い「大国への道」を自ら閉ざした。
習近平の3つ目で最大の「錯誤」は憲法を改正、国家主席の任期を撤廃、自ら「新王朝、新皇帝」への道を着けたことだ。中国共産党は毛沢東の権威化、政権長期化による晩年の政治混乱を反省、鄧小平が1982年に「(国家主席、副主席は)2期を超え連続して就くことは出来ない」との規定を憲法に盛り込んだ。鄧小平は「最後の皇帝」と呼ばれたが、憲法制定から40年、国家主席の任期の歯止めは外れ、新たな「皇帝」が復活する。
なぜ習近平は、そこまで権力志向を強めたのか。様々な要因が考えられるが、習近平が共産党総書記に就任、真っ先に手を着けたのが汚職摘発の「反腐敗」キャンペーン。「虎(共産党の大物幹部)もハエ(公務員や経済人)も叩く」と厳しい摘発に乗り出した。その後、海外逃避の党幹部などを連れ戻して処罰する「キツネ狩り」も行う徹底ぶり。
確かに一党独裁の官僚政治には汚職が起きやすい。その浄化は重要だが、政敵排除の「権力闘争」だったとの見方も強い。習近平は共産党高級幹部の子弟で「太子党」の出身。父親の習仲勲は副首相まで務めたが、「鄧小平に追われ、失脚した」との説がある。鄧小平は文化大革命を否定、「毛沢東の誤り」を認め、「改革開放」へ舵を切った。習近平は思想教育を強化、「父の仇」鄧小平の路線から「毛沢東への回帰」を志向しているのではないだろうか。
経済成長の鈍化に加え、鄧小平の「先富論(先に豊かになれる者から豊かなになろう)」の後遺症とも言うべき「貧富の格差が拡大」して来た。そこで習近平は毛沢東が唱えた「共同富裕(貧富の格差を是正、全ての人が豊かになる)」を持ち出して来た。しかし、国民には「未富先老(豊かになる前に老いる)」懸念が強まっている。
習近平の前任の胡錦濤、その前の江沢民はいずれも「共青団(中国共産主義青年団)」派で、太子党との確執は続いている。「反腐敗」は「共青団」人脈の追い落としでもあったようだ。苛烈な権力闘争で敵をつくり、恨みを買った。権力を手放すと、報復を受ける恐れが強い。習近平は「辞められない状況」と見るのは皮相過ぎるだろうか。
「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対に腐敗する」。英国の歴史家、ジョニー・アクトンの言葉を引くまでもない。習近平は「反腐敗」 のブーメランに襲われかねない。日中国交正常化から半世紀、「新皇帝の中国」と日本はどう付き合っていくべきか。
僕は50年前、日中国交回復に伴い、役目を終える日中覚書貿易の最後の交渉団(岡崎嘉平太団長)に随行記者として訪中した。約3週間中国に滞在し、北京、上海、重慶、桂林、武漢など8都市を訪問した。行く先々で熱烈歓迎を受け、各市の革命委員会幹部から「(中日両国は)一衣帯水の隣国であり、子々孫々までの友好親善を望む」と異口同音の挨拶を受けた。この半世紀で日中の交流は経済、文化、人の面で飛躍的に拡大した。しかし、肝心な政治面での友好関係はどれだけ前進しただろうか。
今の自民党には「親中派」と見られると、「肩身が狭い」との空気がある。「政冷経熱」と言われ、久しい。政治面の交流は50年前の日中国交正常化の時よりむしろ後退しているのではないだろうか。
日本の「尖閣列島の国有化」からも今年は10年。「台湾有事」といきり立って軍拡に走っても事態は改善しない。日中国交正常化50年を機会に日中両国は幅広い交流を見直し、特に政治・外交面の人的交流を活発化し、コミュニケーションを密にして「子々孫々の友好と発展」を目指すべきではないだろうか。
(敬称略)
2022・8・29
上田 克己
プロフィール
上田 克己(うえだ・かつみ)
1944年 福岡県豊前市出身
1968年 慶応義塾大学卒業 同年 日本経済新聞社入社
1983年 ロンドン特派員
1991年 東京本社編集局産業部長
1998年 出版局長
2001年 テレビ東京常務取締役
2004年 BSテレビ東京代表取締役社長
2007年 テレビ大阪代表取締役社長
2010年 同 代表取締役会長
現在、東通産業社外取締役、日本記者クラブ会員
趣味は美術鑑賞

第24回『「プーチン・ショック」の「エネルギー危機」をどう乗り切るか(産業の興亡・企業の盛衰〜Part4)』