第30回『帰って来た日産、自動車の「大変革~Eショック」に勝ち残れるか日本メーカー(産業の興亡・企業の盛衰~part5)』
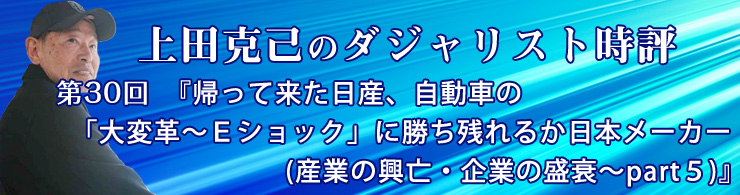
帰って来た日産、自動車の「大変革~Eショック」に勝ち残れるか日本メーカー(産業の興亡・企業の盛衰~part5)
日産自動車が仏ルノーの出資比率引き下げに成功、「独立した日本メーカー」に復帰した。世界の自動車業界は「E(電動化)ショック」とも言うべき大変革期に直面している。世界一のトヨタ自動車に日産も加わった「日本車軍団」はこの大波を乗り切れるか。日本の「自動車産業の興亡」に留まらない「モノづくり産業国家・日本の存亡」がかかっている。
ルノーは日産の株式43%超を握る親会社だったが、事業規模、業績は日産が上回る。ルノーにとって日産は「虎の子の子会社」。その持株比率を15%まで引き下げ、双方対等な出資関係とし、「日産の経営支配権を放棄した」のは何故か。
1つは「ロシアのウクライナ侵攻」が引きガネ。ルノーは「プーチンの暴挙」に対し、フランスに次ぐ主要市場だったロシアからの撤退を決断。損失は20億ユーロ(約2800億円)にのぼり、昨年12月期決算は赤字転落。同じく撤退を決めた日産の損失の2.5倍以上。この損失を埋めるため、敢えて「日産株の譲渡・売却に踏み切った」と推察する。
一方、ルノーはEV(電気自動車)事業を分離し、新会社「アンペア」を設立、日産の15%出資を仰いだ。世界の自動車業界の大変革の方向は「EV化」と「自動運転化」へ向かっている。この2大潮流に「乗れるか否か」に「企業の命運」がかかっている。ルノーは「日産との関係」は、「EVで協業」が出来れば、「虎の子も手放していい」と判断したのが2つ目の理由だろう。
「ウクライナ戦争」で日本の「北方領土奪還」は、遠退いて仕舞ったが、日産自動車が「日本へ戻って来た」。
日産がルノーの傘下ヘ入ったのは四半世紀前の1999年春。巨額な負債を抱え、経営危機の日産に仏政府が後ろ盾のルノーは6千億円超の資金を投入、筆頭株主となった。そして経営再建の責任者としてカルロス・ゴーンを送り込んで来た。ゴーンは1年余りで日産を黒字転換、「ゴーン・マジック」と称賛された。
しかし、当時、テレビ東京の株式上場を準備していた僕は、「ゴーン流の経営改革」に疑問を感じた。東証1部上場を目指していたテレビ東京は既存株主20社ほどに「上場前の増資引き受け」をお願いした。当時の市場状況では既存株主にメリットのある提示だった。
ところが日産は「上場前の増資、新株引き受けを断わる」だけでなく、「持ち株も全て手放したい」と唯一、持ち株売却を申し入れて来た。「本業に関係ない有価証券は全て売却」とのゴーンの「御達し」が出ていた。加えてゴーンは5工場をを閉鎖、不動産の売却、系列企業を半減、従業員2万人削減などを断行した。
「売れるモノは全て売り、切れるモノは全て切る」。欧州産業界でも名を馳せた「コスト・キラー」の面目躍如。それが出来たのはゴーンが日本の業界に「しがらみが無い」外国人経営者の「強さ」であり、「凄さ」でもあった。僕が親しかった日産の役員は「取締役会が英語になり、反論は難しい」とボヤいていた。
ここまでやれば日産のような大規模会社は含み資産も多く、「収支は好転」する。ただ、企業としての総合力は「トヨタの3分の1以下」に縮小したのではないだろうか。それでもゴーンは「日産再建の救世主」として19年間も最高経営責任者(CEO)として君臨した。更にその功績でルノーのCEOに登りつめた。
ゴーンが最終的に目指したのは「ルノーへ日産を併合」、三菱自動車や他の欧米メーカーも糾合した「世界一の自動車グループ」の形成だった。この計画はマクロン大統領の要望でもあり、実現すれば、ゴーンは「フランス最大最強の企業経営者」としてフランスの「エスタブリッシュメント」へ仲間入りする。レバノン生まれブラジル育ちの「異邦人の野望」は達成目前だった。ところが2018年11月にゴーンは羽田空港で東京地検特捜部に逮捕され、事態は一変した。
逮捕容疑は「役員報酬の有価証券報告書への虚偽記載」などだが、「日産とルノーの統合阻止」を狙った日本人幹部らの「クーデター説」が根強い。それも経済産業省など政府筋と気脈を通じた動き、との疑惑が拭えない。確かにゴーンには「公私混同」や度が過ぎた「お手盛り」があったが、「刑事罰を受ける犯罪行為」だったか。専門家の意見も分かれた。
そうしたデリケートな事態だったが、ゴーンは保釈中に不法に国外脱出、故郷のレバノンに逃避した。希代の「カリスマ経営者」は日本だけでなく、フランス当局も国際手配の「逃亡者」へ転落した。ルノーが日産の出資比率引き下げ要求に応じた3つ目の理由は、「ゴーンの暴走・蛮行」に対し「陳謝」の意向が働いたのではないだろうか。
いずれにしろ「日産の日本回帰」で年間売上げ1兆円超の日本の自動車メーカーは10社に上る。その合計生産台数は中国、米国に次いで世界3位。敗戦後の日本を世界2位の経済大国に引き上げた繊維、造船、家電などの製造業は今や国際競争力を失った。しかし、「高度経済成長の仕上げ役」の自動車は、世界のトップクラスの地位を、今だ維持し、GDP世界3位の日本の製造業を辛うじて支えている。
自動車は人類が産んだ「最大の商品」。売上規模の大きさ、経済波及効果の広がり、人々の生活や文化への影響度からも「比類無き商品」。その自動車が「世紀の大変革のモデル」として達成を競っているのが「自動運転化とEV化」。特に「EV化」は「脱炭素の気候変動対策」としても推進が急務で、世界の自動車メーカー経営者はこぞって「EVファースト」を課題に掲げている。最近、新聞で「EV」の活字を見ない日は無く、「大変革」は「Eショック」の様相を呈している。
現在、EV戦略で先行しているのは米国のテスラ。創業20年余りのベンチャー企業だが、その時価総額は2020年にトヨタを抜いて自動車企業では「世界一」となった。CEOのイーロン・マスクの個人資産は21年に人類史上初の3千億㌦(30兆円超)を超えた。
僕は1970年に日経新聞で自動車業界を担当して以来、世界の業界動向を注視して来た。その中で自動車のような高額商品を量産・販売、巨額な設備投資を要し、裾野の広い産業にあって、時価総額とは言え「ベンチャー企業が短期間に世界一になる」とは予想だにしなかった。
「テスラの奇跡」は「ChangeはChance」、「変革期にビジネス・チャンスあり」を実証した。だが、変革は企業の再編・淘汰も伴う。世界の自動車業界の「EV戦争」は既存の自動車メーカーの「EVシフト」に加え、グーグル、アップルなどGAFAを始め、ソニーなど異業種参入の動きもあり、これからが本番。ポスト「Eショック」の業界地図は大きく変貌するに違いない。テスラの地位ももちろん安泰ではないだろう。
EV化に先行した企業はテスラだが、国では中国。22年の世界のEVの販売台数は約780万台と推定されているが、その3分の2を中国が占める。
中国は液晶ディスプレイで標準化したテレビ・携帯電話の生産で韓国の後塵を拝した。その反省から習近平は15年にEVでモジュール化した自動車生産では先行し、世界トップの「製造強国」を目指す方針「中国製造2025」を打ち出した。政府の支援を受けた中国のEVメーカーは急成長、中でもBYDはテスラを凌ぐ勢い。今年初め、BYDは日本に販売店をオープンした。日本に上陸した中国製自動車がどう受け止められるか、「Eショック」の注目点の1つだ。
その中国、そして米国と並んで日本は目下、世界3大自動車生産国の一角を占めている。だがEV化で「米中に遅れ」をとっている。トヨタはハイブリッド車で先行したためEV転換への踏み切りが遅れた。ホンダも高性能ガソリンエンジンへのこだわりからEV化に出遅れた。その中では日産が数少ない「ゴーンの遺産」により「EV化に先行」しているが、生産台数の世界ランクは7位程度。
22年はEVが世界の自動車販売の10%に達し、「EV化元年」と言われている。「日本は出遅れた」のは事実だが、まだ「巻き返し」は出来る。今年に入ってトヨタを始めスバル、マツダ、いすゞと「社長交替」が相次いでいる。いずれの新社長も「EV化推進」を異口同音に強調、社長交替の狙いが「EV化シフト」であることを示している。
「EV化」はこれまでの自動車とは違う「新しい商品づくり」である。バッテリーやモーターなどガソリンエンジン車と違った部品やソフトウェアが重要になる。充電ネットワークなどの新しい利用・交通インフラの整備も欠かせない。だから一企業の取り組みでは「EV戦争」には勝てない。
いかに関連企業と連携し、新たな技術や商品を開発出来るか。国や自治体が充電インフラ整備などを助成し、EVの需要喚起策をとれるか、などがカギとなる。最終的には企業集団や国単位の戦いとなる。
23年度の日本の国家予算は110兆円を超えたが、「1兆円超え」は僕が小学校の下級生の頃。従兄の大学生に「アメリカのGMという自動車会社の売上げが同じ」と教えられ、そんな「巨大会社があるのか」と驚いた。半世紀前、日経の駆け出し記者で自動車業界を担当した時の最重要テーマは「米国ビッグ3(GM、フォード、クライスラー)の日本への資本上陸」だった。
日夜、ビッグ3関係者の来日を航空会社の乗客名簿でチェックした。こうした取材の積み重ねで日本の「貿易資本の自由化政策」の極め付き事例である「GM、いすゞ自動車へ資本参加」を日経が特報した。
嘗て「GMによいことはアメリカにもよいこと」とGM会長が言って憚らなかった。GMは「米国のシンボル」的存在。そのGMも創業100年を迎え、経営危機に直面、政府へ救済を求めた。そして敗戦国の「日本のトヨタ」「ドイツのVW」に生産販売台数で抜かれた。
GM衰退の原因には「覇者の驕り」があったのではないか。大企業病である「組織の官僚化」で環境変化への素早い対応力を失った。GMに代わって「覇者の座」に着いたトヨタに「驕り」は無いか。「創業家から番頭経営」に14年ぶりに切替えた「トヨタの行くえ」に注目したい。
日本はWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)で中国、韓国、メキシコそして米国を劇的に破り、世界一になった。米国の「国技」とも言える野球で日本が米国に勝ち、MVPの大谷翔平を始め「侍ジャパン」のメンバーは「日本人の進化」を実感させてくれた。
それに引き換え、肝心な日本の経済・産業は、この30年間、国際競争力は低下の一途。世界ランクは1992年までの1位から2022年は34位まで転落している。スマホ、半導体、再生可能エネルギー、新感染症ワクチン、EVなど先端製品分野で日本は中国、韓国、そして米国などに出し抜かれっ放し。今年に入ってもJAXAの「ロケット打ち上げ失敗」、三菱重工の「国産航空機の開発断念」、パナソニックとソニーの統合の「有機EL事業の経営破綻」と日本の連敗は止まらない。
各分野の企業の競争力低下が原因だが、驚異の経済成長を実現、ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われた官民一体の「日本株式会社」を主導した経済産業省の「政策失敗」も看過出来ない。
ただ20世紀のリーディング・インダストリーの自動車産業ではトヨタがGMを抜き、ホンダ、日産グループなども世界の中上位メーカーとして踏み止まっている。自動車産業は21世紀も「Eショックの変革」を遂げることで、製造業の中核産業として存続しそうだ。「モノづくりニッポン」にとって自動車業界の競争力維持が経済力回復の「最後の砦」となる。 だから日本の自動車メーカーは「Eショック」を何としても乗り切り、勝ち残らなければならない。
今年は日本はG7の議長国。岸田首相は地元の広島でこの5月にサミットを開催する。加えて日本は今年から国連・安全保障理事会の非常任理事国にも選出されている。その日本の「外交の武器」は何か。「ミサイルや戦車」ではない。「経済力」である。
それがこの30年間も衰退続きでは「日本ならではのリーダーシップ」が取れるはずはない。この流れに歯止めをかけるには、世界の自動車産業を襲う「Eショック」に対し「日本車軍団」が「侍ジャパン」に続く「逆転打を打つ」しかない。「やっちゃえ、トヨタ、ホンダ、ニッサン」。
(敬称略)
2023・3・30
上田克己
プロフィール
上田 克己(うえだ・かつみ)
1944年 福岡県豊前市出身
1968年 慶応義塾大学卒業 同年 日本経済新聞社入社
1983年 ロンドン特派員
1991年 東京本社編集局産業部長
1998年 出版局長
2001年 テレビ東京常務取締役
2004年 BSテレビ東京代表取締役社長
2007年 テレビ大阪代表取締役社長
2010年 同 代表取締役会長
現在、東通産業社外取締役、日本記者クラブ会員
趣味は美術鑑賞

第29回『岸田政治への失望と危惧~軍拡・原発の推進を問う』