第12回 『日本版「産業の興亡、企業の盛衰」記』
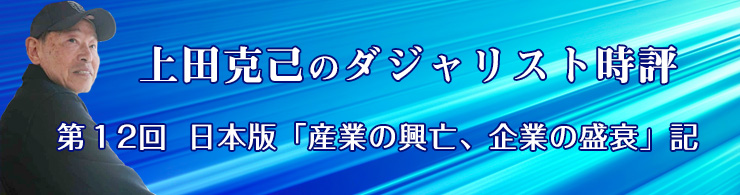
日本版「産業の興亡、企業の盛衰」記
新型コロナ・パンデミックは日本そして世界の政治、経済、社会を大きく変革する契機となりそう。特に経済面では歴史的な「産業の興亡」、多数の「企業の盛衰」が起きそう。僕は1968年に新聞記者となって以来、半世紀超、内外の産業・企業の動向をウォッチして来た。コロナ・パンデミックが起因の世界的な「産業・企業の新潮流」を前に、僕が目撃した「産業の興亡・企業の盛衰」を振り返る。今回はそのPart 1。
戦後の日本産業界で企業の売上高の浮沈、製品シェアの変遷は数多発生した。その中で「奇跡」と思われた「大逆転劇」が2つある。1つは「アサヒビールが麒麟麦酒を抜き、ビール業界の首位を奪還」。もう1つは「シャープが松下電器(パナソニック)とソニーをテレビ販売で上回り、テレビメーカー日本一へ躍進」。
まずビール界の「奇跡」。日本のビールは戦後、1980年代半ばまで「どのメーカーの製品か」識別が難しかった。製品の差別化、多様化は停滞、「どういうわけかキリンです」のキャッチフレーズ通り、キリンが圧倒的シェアを誇った。客に銘柄指定の習慣もなく、飲食店で「とりあえずビール」と言えば、キリンが出て来た。キリンのシェアは60%を超え、独禁法上、問題視され、「企業分割」が真面目に議論された。
このためキリンは広告を自粛、設備投資も抑制して「自ら売れ行きにブレーキをかける」異例の経営方針を取った。
一方、アサヒビールはシェアが一桁に転落、最下位のサントリーに並ばれそうな低迷ぶり。「夕日ビール」と揶揄され、泡と消えそうな儚い存在に。
窮状を見かねた旭化成は、社名が「あさひ」の同名の「好」か、社内でアサヒビールを飲む応援パーティーを開いた。更に旭化成の城下町の宮崎県延岡市ではアサヒビール愛飲運動を地域社会に呼び掛けた。
こうした状況下で、アサヒビールの労組の委員長、書記長から「会いたい」と申し入れがあった。僕は日経の食品業界担当記者と一緒に銀座のビアホールでご馳走になった。彼らはアサヒビールの問題点・経営再建策について産業界や我々記者の「意見を聞きたい」と、切実だった。
この時の書記長が後にアサヒビール11代目の社長となる泉谷直木氏。約30年後、僕は泉谷氏の社長就任パーティーへ出席、名刺を渡すと、「銀座のビアホールで会って以来ですね」と言われて驚愕した。
アサヒビールは1987年1月、「コクとキレ」の新商品「スーパードライ」を発売。これが大ヒット、2001年にアサヒのビール類売り上げはキリンを抜き、48年ぶりに1位を奪回した。
次に「家電の王様」と言われたテレビで、シャープが起こした「奇跡」。 戦後、テレビは自動車と並ぶ大型消費財で日本の高度経済成長を牽引した。テレビ市場のシェアは販売力の松下とブランド力のソニーの2強が上位を固め、シャープは「万年3位」以下だった。
しかし、2001年にシャープが「液晶テレビAQUOS(アクオス)」を発売、2004年に三重県亀山工場でAQUOSを生産すると、「亀山ブランド」と名指しされ、爆発的に売れた。テレビのディスプレイはブラウン管から液晶へ劇的に転換、シャープは一気にテレビのトップメーカーとなった。
2007年大阪へ3度目の赴任をした僕は、シャープの町田勝彦社長へ挨拶に伺い、「シャープがテレビで松下、ソニーを抜いたのは日本の産業史に残る快挙」と持ち上げた。すると「韓国勢の追い上げに会って大変なんだ」と町田社長。韓国製テレビにお目にかかったことがなかった僕が「まさか」と驚くと「政府と一体だから手強い」と厳しい表情。 町田社長の懸念は当たった。
韓国のサムソン電子が安価な液晶テレビを量産、海外市場を席巻、日本メーカーのシェアを奪った。液晶パネルの価格も下落、シャープは2009年度に株式上場来、初の赤字へ転落。その後も業績が低迷、2016年に台湾の電子機器受託メーカー、鴻海(ホンハイ)の傘下へ入った。「韓国企業との競争に敗れ、台湾企業に買収される」。明治維新以来の日本産業史で予想し難い現象が起きた。「黒船来航」「敗戦」に次ぐ「第3の開国」と言われる「グローバル経済」の所産だ。
戦後の日本産業史に残る「奇跡の逆転劇」を演じたアサヒビールとシャープ。アサヒは今なお、キリンと首位を争っているが、シャープは台湾企業の子会社となった。この差はなぜ起きたのか。
アサヒ、シャープともヒット商品を開発したタイミングを逃さず、「選択と集中」、その商品の増産の設備投資と拡販に力を入れた。「一本足打法」と揶揄されたが、それほど集中しなければ「奇跡の逆転」は起きなかった。
ただビールは市場がドメスティックで市況商品ではない。増産しても値崩れはしない。これに対してディスプレイが液晶パネルとなり、モジュール化したテレビは市況商品化。韓国勢の積極的な設備投資、増産で値下りした。シャープは「日本で勝ったが、世界で敗れ、台湾企業の軍門に降った」。商品が「ドメスティックかグローバルか」で、明暗を分けた。
経営危機に陥った時の「経営者の決断力、資質」と「組織の団結力」「支援の有無」も大きな明暗要因。
アサヒビールはシェア最下位へ転落しかねない危機に直面して住友銀行から村井勉氏、樋口広太郎氏と2代続いて社長を受け入れ、スーパードライのヒットを演出、トップ企業へ返り咲いた。その実現の裏には労組も強い危機感を抱き、労使一体で経営再建に取り組んだ。住友銀行だけでなく、企業集団が異なる旭化成なども支援に動いた。この「団結力と幅広い応援団の存在」が経営再建を可能にした。
これに対してシャープは、液晶路線へ舵を切った町田氏が、それを更に推進するため49歳の「液晶のプリンス」片山幹雄氏を後任社長に大抜擢。「吉永小百合(シャープのCMキャラクター)と小谷真生子(テレビ東京番組WBSのキャスター)以外は全て君に譲る」と町田氏は片山社長へ全面的な権限委譲を表明した。
しかし、シャープの業績が急激に悪化すると、過大投資となった堺工場新設などがヤリ玉に。「目の付け所がシャープでしょう」と自ら誇った「液晶路線」に社内外から批判の声が上がり、町田・片山ラインにも亀裂が生じた。結局、町田会長と片山社長が刺し違える形で退任、業績悪化の責任を取った。その結果、危機に必要な強いリーダーシップを欠き、社内は分裂、優秀な人材も離散した。
シャープの経営トップは伝統的に財界活動を敬遠、元々経済界で「孤立した存在」だった。だから経営危機に陥っても有力な応援団は現れず、外資に頼らざるを得なくなった。 21世紀に入って世界経済はコンピュータリゼーションによる「デジタル革命」と気候変動対策として脱炭素化による「エネルギー革命」が急速に進みつつある。
新型コロナ・パンデミックによる「コロナ・ショック」はこの2大革命を加速、日本そして世界に大きな「産業の興亡と数多くの企業の盛衰」をもたらすだろう。「新たなPC(ポスト・コロナ)の時代」の日本は、こうした経済動向を睨み、コロナ禍で炙り出された「日本の劣化と衰退」に歯止めをかけ、「逆転」を演出しなければならない。
2021・6・5
上田 克己
プロフィール
上田 克己(うえだ・かつみ)
1944年 福岡県豊前市出身
1968年 慶応義塾大学卒業 同年 日本経済新聞社入社
1983年 ロンドン特派員
1991年 東京本社編集局産業部長
1998年 出版局長
2001年 テレビ東京常務取締役
2004年 BSテレビ東京代表取締役社長
2007年 テレビ大阪代表取締役社長
2010年 同 代表取締役会長
現在、東通産業社外取締役、日本記者クラブ会員
趣味は美術鑑賞

第11回 『コロナ世界大戦・敗戦日本』