第13回 『「石油」の終わり。怖いのは「オイル(油)より老いる・ショック」~「産業の興亡・企業の盛衰」Part2』
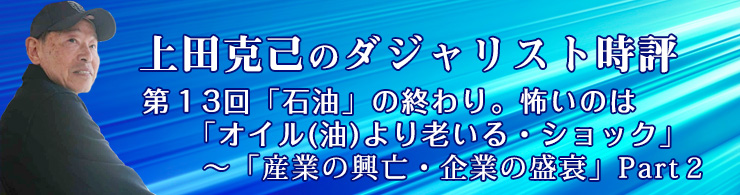
「石油」の終わり。怖いのは「オイル(油)より老いる・ショック」~「産業の興亡・企業の盛衰」Part2
7月6日の日本経済新聞の夕刊の1面トップに「OPEC(石油輸出国機構)」の文字が踊った。夕刊ながらOPECが1面トップ記事になるのは久しぶり。あの「オイル・ショック」を引き起こした「OPECの復権」なのか。記事からは、むしろ「OPEC崩壊」の「弔鐘の音」が聞こえる。先の20世紀は「石油の時代」と言われた。21世紀に入って20年余、「『石油』の終わり」が始まっている。
実は日経のトップ記事の主語はOPECではなく、正確には「OPECプラス」。OPECプラスは、OPECとロシアなど非OPECの産油国が石油価格安定のため協力しようと2016年に結成した組織。
6日の記事は、OPECプラスが1日から続けてきたオンラインの「閣僚協議を中止。原油の減産縮小が延期され、ニューヨーク市場の先物価格は1バレル77㌦弱と6年半ぶりの高値」と伝えた。「協議中止」の原因はサウジアラビアとロシアの合意案にOPECの主要メンバーのアラブ首長国連邦(UAE)が反対したからだ。OPECの「結束力の弱さ」がまたも露呈した。
僕が1983年3月にロンドンヘ赴任したのは、OPECのロンドン総会が開幕する2日前。この総会は1973年の第1次オイル・ショックから10年間続いたOPECによる原油価格の引き上げが「引き下げ」に転じた「歴史的総会」だった。以来、臨時を含めOPEC総会を、僕は11回取材した。場所はスイスのジュネーブが多く、次いでオーストリアのウィーン。フィンランドのヘルシンキへも出掛けた。
35年以上前だが、OPEC取材で得た印象は「まとまりの悪さ」と「サウジ主導の組織」の2点。
僕が初めて取材したロンドン総会では、各国の代表は「会議に遅刻したり、途中で抜け出したり」が散見され、会議は「何時に始まり、終わったかさえ、はっきりしない」有り様。これが「日本を震撼させて来たOPECの総会か」と唖然とした。
この実態を目の当たりにして僕は、映画「アラビアのロレンス」の一場面を想起した。ロレンスとアラブ人部隊がトルコ支配のダマスカスを攻略、開催した「アラブ国民会議」が各部族のエゴの応酬で決裂し、ロレンスは深く失望する。65年前の会議と見紛う状況は、その後、表向きは解消された。
しかし、OPECは総会毎に協定を結んでも、協定破りが横行、「ロンドン総会」を契機に世界の石油市場への影響力を弱めて行った。それでも「世界最大のカルテル」と恐れ、警戒する向きもあったが、僕は「OPECは『張り子の虎』」と、ずっと見なして来た。
とは言えOPECがカルテルとして世界の石油市場に一定のインパクトを与え続けてきたのも歴史的事実。それは「サウジアラビアの存在とそのリーダーシップ」による。圧倒的な原油生産力・価格競争力を誇るサウジが生産量調整役の「スイング・プロデューサー」を演じて来たからだ。そのサウジの指揮官がアマハド・ザキ・ヤマニ石油相だった。
サウジ初の弁護士か ら1962年に石油相に抜擢されたヤマニは24年間も在任、「ミスターOPEC」と称された。あご髭と鋭い眼光で威厳さえ感じさせた。総会が終わり、スポークスマンが記者発表しても、ヤマニの単独会見を聞かないと世界各国の記者は「OPEC総会を総括」出来なかった。そのヤマニも原油価格の下落の責任を問われるかのように1986年に解任された。そしてサウジは「スイング・プロデューサー」の役割を放棄した。
20世紀は産業史的には「石油と自動車の時代」。その「石油」の世界の主役は「セブン・シスターズ」と呼ばれたエクソンなどの国際石油資本(メジャーズ)とOPECだった。ヤマニ解任は、その「OPECから主演俳優が去り、一つの時代が終わった」と印象付けた。
その後、ニューヨークの原油先物価格は2008年7月には1バレル147㌦の史上最高値を付ける局面もあったが、必ずしもOPECによる生産調整の結果ではなかった。それよりも中国を始めとするアジアの需要増や原油先物市場への投機マネーの流入の影響が大きかった。
この原油価格の高騰が米国のシェール・オイルの開発を促した。シェール(頁岩)層に含まれた石油、ガスを取り出す技術が開発され、米国は原油輸入国から輸出国へ40年ぶりに転じた。この「シェール革命」が再び原油価格の抑制、下落を招いた。
これに弱体化したOPECはもちろん、ロシアなどの非OPEC産油国も対抗出来ず、双方は歩み寄った。そして「OPECプラス」が誕生した。
しかし、組織は大きくなっても、カルテルの威力が「プラスされた」訳ではない。サウジとロシアがようやく合意した「減産縮小案」も、サウジの弟分のUAEが反対する始末で、「まとまらない」体質は変わらないからだ。
世界的な気候変動とコロナ・パンデミックで世界に「脱炭素」の動きが急加速して来た。その具体策として「EV(電気自動車)と再生可能エネルギー」への転換が猛烈な勢いで動き始めた。これに伴い20世紀以来、増大を続けた石油需要は減少に転じる「石油需要ピーク説」が現実となってきた。「ピークは既に2019年だった」との説もあり、「石油の終わり」が始まっている可能性が高い。これまでは石油資源は「有限で、いずれ枯渇する」。生産力が頂点に達し、増産出来ないと、価格高騰を招く「ピークオイル説」が心配されて来た。
しかし、引退したヤマニは2009年、日経記者のインタビューに応じ「石器時代は石が無くなったから終わったのではない。(青銅器、鉄器など)石に代わる新しい技術が生まれたから終わった。石油も同じだ」と喝破した。そのヤマニは「石油の終わりの始まり」に殉じたかのように今年2月、ロンドンで死去した。享年90歳。
日本は第一次オイル・ショック以来、「脱石油、脱中東」 を目指して来た。それはエネルギーの大宗を占める石油が余りに「不安定」で、それに依存した経済は「油上の楼閣」と危惧されたからだ。原油生産の主導権を握るOPECの「まとまりのなさ」に加え、原油の埋蔵、生産力が「世界の火薬庫」と言われる中東に偏在しているためだ。
中東を舞台の小話がある。カメが紅海の向こう岸へ渡ろうしたところ、サソリが背中へ乗せて行ってと頼んだ。カメは刺される恐れがあるからと断わると、サソリは「カメを刺せば自分も溺れるので、そんなことはしない」と。カメは納得してサソリを背中に乗せ、紅海の真ん中辺へ。すると突然はサソリはカメを刺した。カメが「なぜだ」と叫ぶ。サソリは「ここは中東だ」と答えた。
中東は「不可解な世界」とのブラック・ユーモア。だが世界から「極東を見る」とどうだろう。北朝鮮の存在は「サソリとカメの舞台を日本海へ移しても成立」する。
ともかく「オイル・ショック」を契機に日本は「脱中東、脱石油」を目指し、「原子力発電」に舵を切った。その戦略が福島原発事故による「アトミック・ショック」で破綻した。日本のエネルギー構成は「オイル・ショック」以前の「中東石油依存」へ逆戻りした。
しかし、アトミック・ショック後の方策は明確だ。「脱石油、脱中東」に代わって「「脱原発、脱炭素」。それを実現するためには「再生可能エネルギーの開発促進」しかない。
OPECとメジャーズ支配の「石油の時代」は終わった。日本が恐れ、対応したければならないのは「オイル・ショック」ではなく「老いる・ショック」だ。
日本の「老いる」は人口の「高齢化」だけではない、社会インフラの「老朽化」だ。57年前の東京五輪に備えた首都高速道路などの突貫工事が耐用年数を迎えている。「東京2020」を、東日本大震災の「復興五輪」とするなら場所が違う。仙台開催ならともかく東京でやるなら「修復五輪」とすべきだった。まして「コロナに打ち勝つ証」と取って付けるのは政治利用の茶番劇。
コロナ・パンデミックで東京五輪のテーマ・意義付けは全て消し飛んだ。東京都と日本政府に残るのは恐らく「膨大な財政赤字」だけだろう。これでは肝心な「老いる・ショック」対策は出来ない。日本が東京五輪でいくらメダルを獲得しようが、「日本の老化、地盤沈下」は進む一方ではないだろうか。
2021・7・14
上田 克己
プロフィール
上田 克己(うえだ・かつみ)
1944年 福岡県豊前市出身
1968年 慶応義塾大学卒業 同年 日本経済新聞社入社
1983年 ロンドン特派員
1991年 東京本社編集局産業部長
1998年 出版局長
2001年 テレビ東京常務取締役
2004年 BSテレビ東京代表取締役社長
2007年 テレビ大阪代表取締役社長
2010年 同 代表取締役会長
現在、東通産業社外取締役、日本記者クラブ会員
趣味は美術鑑賞

第12回 『日本版「産業の興亡、企業の盛衰」記』