第14回 『非常事態下の「東京2020」を終え、懐かしの「1964年東京オリンピック」を想う。』
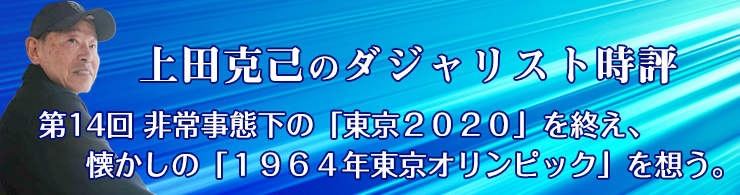
非常事態下の「東京2020」を終え、懐かしの「1964年東京オリンピック」を想う。
1年延期で、無観客の歴史に残る「東京五輪」が閉幕しました。コロナ・パンデミックの拡大に対応した「非常事態宣言」下の「異常五輪」でした。開催に疑問を感じても、競技が始まれば、「スポーツ好き」の僕はついテレビを見てしまいました。競技を楽しみ、感動もしました。それでも「東京2020」には幾多の疑問と課題が残りました。開会式と閉会式に象徴された「東京2020」を検証、57年前の「東京オリンピック」を回想しました。
僕は開会式の夜は体調不良で、テレビ中継は断片的にしか観ていません。それでもビデオを見たり、家族の意見 を聞いて感じたのは「開会式にサプライズが少なかった」。東日本大震災からの「復興」やコロナ禍の「克服」をアピールするメッセージ性も乏しく、「日本の伝統や文化」を印象付ける演出も弱かった。
特に僕は聖火リレーのランナーに「長嶋・王・松井の巨人軍OBトリオが登場した」のに違和感を覚えました。「アンチ巨人」だから異を唱えるのではありません。 長嶋・松井の国民栄誉賞の「同時受賞」の時に感じた「政治家の思惑」です。松井と同郷の「森喜朗の影」です。それが2021年の「東京五輪」で再現されたのは釈然としません。
オリンピックの聖火リレーはオリンピックを盛り上げる事前セレモニー。開催国の各地を走るランナーは各々の地域の思惑、事情で人選すればいい。
しかし、開会式でメインスタジアム内をリレーするランナーは全世界へ放映され、大会テーマのアピール役です。だから「五輪の理念や歴史、開催国が五輪に懸ける狙い、想い、そして文化を体現出来る人が登場すべき」です。
その点、王はともかく長嶋は「国民的人気者」であっても、五輪への参加実績もないはずです。大多数の世界の視聴者は「聖火ランナーのユニフォームを着た身体不自由な老人とそれを支える2人の男」に奇異な感じを抱いただけでしょう。
身体不自由な元アスリートの聖火リレーでは1996年アトランタ五輪の「モハメド・アリ」を思い出します。でもアリは1960年ローマ五輪のボクシングの金メダリストです。ベトナム戦争の兵役拒否や公民権運動に参加、政府と対立して来ました。アリの起用はオリンピックが政治・政権に対し「独立した存在」と感じさせました。
オリンピックはスポーツの祭典だから「日本のスポーツ界のレジェンドを登場させる」との意図かも知れません。それなら今や「伝説化」した「1964年東京オリンピック」で活躍したアスリートOBを登場させるべきだったのではないでしょうか。今回、いろんな意味で無理筋の「東京五輪」が強引に誘致、開催されたのは石原慎太郎や安倍晋三だけでなく、日本国民に広く「東京オリンピックへの強いノスタルジア」があったからです。
「東京1964」で活躍したアスリートで健在な方と言えば、女子バレーボールの「東洋の魔女」のメンバーや重量挙げの三宅義信の名前が浮かびます。 しかし、僕の勝手な推薦は「マラソンの君原健二」です。理由は前回の東京五輪で、僕がナマで見たアスリートで「健在なのは君原だけ」だからです。
東京五輪が開催された1964年10月は僕が九州の片田舎から上京して1年半。当時、明治神宮の森が窓から見える代々木のアパートに住んでいました。千駄ヶ谷の国立競技場も歩いて行ける距離で、テレビを見ながら競技場の歓声が聞こえるような錯覚・興奮状態に陥っていた気がします。
ただ主な競技場のチケットは入手できず、唯一、競技場に入れたのは秩父宮ラグビー場。アラブ連合共和国(当時のエジプトの呼称)とチェコスロバキア(だったと思う)のサッカーの試合を観戦しました。
もう1つ、ナマの競技が見れたのは「マラソン」です。アパートでテレビを観ていて、先頭のアベベが甲州街道を調布で折り返し、新宿に近付いて来るのを見計らって、現在の新宿駅南口近くに駆け付けました。しばらく沿道で待っていると、黒いアベベの姿が左後方に見え、ぐんぐん近付いて来ました。そして目の前を背筋を伸ばし、表情一つ変えず、白いシューズを履いたスマートな肢体が通り過ぎて行きました。
87歳の歌人、窪田空穂は「アベベ走る 群を抜きてはひとり走る リズムに乗りて静かに速く」と歌いました。
ナマを観た僕には今でもこの時のアベベの残像がまぶたに焼き付いています。アベベの印象が余りに強烈で美しかったので、後続の円谷幸吉や英国のヒートリーの印象はほとんど残っていません。
それでも僕は「君原だけは見届けて、アパートへ戻り、テレビで結果を見たい」と思っていました。それは君原が同郷の福岡県人、それも僕の郷里の豊前市に近い北九州市小倉の出身で、八幡製鉄の社員だったからです。僕は君原に、かねて親近感を持ち、ファンでした。
君原は円谷からも数分遅れて首を左に傾けた独特の苦しそうな表情で現れ、走り去って行きました。この時の君原の表情、走るスタイルは人間的。超然とした「哲人アベベ」と対照的で忘れられません。
東京五輪のマラソンはアベベが世界記録で金、ローマに続いて史上初の2連覇。スタジアムのトラックで円谷を抜いたヒートリーが銀、円谷は銅でした。日本選手で最も下馬評が低かった円谷が、日本の陸上陣唯一のメダルを獲得しました。だがこの「栄光が悲劇の引き金」でした。
3年3ヶ月後、メキシコ五輪の開催を控え、円谷は「父上様、母上様、三日とろろ お美味しゅうございました。(中略)幸吉はもうすっかり疲れ切ってしまって走れません。(中略)幸吉は父母上様の側で暮らしとうございました」との遺書を残して自死した。享年27歳。
円谷の死については様々な原因が語られて来ましたが、「平和の祭典」を謳いながら国家間の「国威発揚の戦場」と化した「オリンピックの戦死者」です。円谷の遺書が「日本人の心を強く打った」のは先の大戦の戦没学徒遺稿集「きけ わだつみのこえ」に通じるものがあったと感じました。
円谷の苦悩を誰よりも「理解したのは君原でした」。東京オリンピックで最も期待された君原は8位の選外(当時の入賞は6位まで)で、つらい思いをし、円谷のメダル獲得で救われた面もあったからです。君原は弔文で「メキシコで日の丸を掲げる」と、同学年の亡き円谷に誓いました。そしてメキシコ五輪で、君原は見事、銀メダルを獲得しました。
更にミュンヘンでも5位入賞、ボストン・マラソンにも優勝しています。現役時代の35回、さらに引退後に参加した生涯合計74回のマラソンを君原は「全て完走」しました。同じ九州出身で「日本マラソンの父」と言われている 「いだてん」の金栗四三も遠く及ばないアスリート精神。まさに「アスリートの鑑」です。
君原ほど、57年振りの「東京五輪」の最終聖火リレーのランナーに相応しい「アスリートのレジェンド」はいません。
ところが日経新聞の北川和穂編集委員の記事で知ったのですが、80歳の君原は今年の3月27日に福島県須賀川市を聖火ランナーとして走っていたのです。なぜ君原は郷里の北九州市ではなく、須賀川市を走ったのか。それは須賀川市は円谷の出身地で、君原は「引退後も同市の円谷記念大会に毎年出場し、墓参りを続けている」からでした。
1964年の東京オリンピックは菅首相が言うまでもなく、「東洋の魔女」の活躍や柔道の「ヘーシングと神永の戦い」など幾多の感動と思い出を残しました。ただ僕の東京オリンピックは「アベベ、君原そして円谷の死」です。
「秋くれば円谷幸吉かなしめる人がわが夫干し柿食みて」
僕の大学時代からの親友で講談社退職後、歌人として活躍した小高賢(鷲尾賢也)の夫人の三枝子さんが詠んだ歌です。彼は残念ながら2014年に急逝しましたが、同世代として共通した想い、経験、価値観を持つ男でした。
57年前の東京オリンピックは10月10日に開会、24日に閉会しました。この閉会の夜、僕は幹事団に加わり、母校、福岡県立築上中部高校(2005年に閉校)の在京同期会を開きました。場所はオリンピック会場に近い代々木駅前のお好み焼き屋でした。防衛大学在学の同期生から「オリンピック閉会式のプラカード要員となったので欠席」の通知がありましたが、集まった同期生は40人近くに上りました。
振り返れば「1964年東京オリンピック」は日本が戦後復興から高度経済成長そして「先進国への仲間入り」へ向かう転換点でした。
我々高校同期生にとっても、生まれて初めて故郷を、親兄弟を離れ、異郷の地で、独立した「人生」という長い孤独な旅へ出発した時でした。思えば「東京1964」の閉会の夜に高校同期生と交わした杯は新しい人生への旅立ちの「別れの盃」だったのでした。
2021年の酷暑に開会した「東京2020」は閉会式も物足りない内容でした。「東京1964」の閉会式は選手団が混然、和気あいあいのパレードとなり、大きな感動を呼び、以後のオリンピックに「東京方式」として踏襲されました。コロナ禍で制約があったとは言え、「東京2020」では新機軸は打ち出せませんでした。ソプラニスタの岡本知高はよかったが、「日本には世界的なエンターテイナーはいないのか」と寂しく思いました。唯一、「ブラボー」と感じたのはパリからの中継でした。
エッフェル塔上にマクロンが登場、塔下にマスクを着けない6千人もの市民が集い、上空ではフランス空軍の「パトルイユ・ド・フランス」がパリの青空に鮮やかなトリコロールを描き、次期「パリ五輪」を印象付けました。マクロンはコロナ対策に成功した訳ではありません。それでも五輪開催を引き継ぐに当たって、ワクチン・パスを出し多勢の市民を動員、「熱いパリ」と「閑散な東京」との対比を炙り出しました。
「東京2020」ほど開催前から数々の不祥事・事件が発生したオリンピックはありません。国立競技場のデザイン変更、エンブレムの盗用、JOC(日本オリンピック委員会)の竹田会長の贈賄疑惑、大会組織委員会の森会長の女性蔑視発言、JOC経理部長の突然死や開閉式典の演出統括やディレクター、音楽プロデューサーの相次ぐ降板。
こうした不祥事続発の底流には巨大な利権構造と化したオリンピックの硬直した組織、人事があります。その組織の頂点に立ち「オリンピックの商業化」を推進するIOC(国際オリンピック委員会)のバッハ会長は「開催国を搾取するぼったくり男爵」(ワシントン・ポスト紙)と揶揄されています。ならばフランスの司法当局から贈賄疑惑で捜査された元皇族の家系の竹田JOC元会長は「ぼったくられ殿下」。いずれの不祥事もその原因はほとんど解明されないままです。
「東京2020」は コロナ禍と酷暑対策が問われただけではない。メダル・ラッシュに目を眩まされてはなりません。(敬称略)
2021・8・12
上田 克己
プロフィール
上田 克己(うえだ・かつみ)
1944年 福岡県豊前市出身
1968年 慶応義塾大学卒業 同年 日本経済新聞社入社
1983年 ロンドン特派員
1991年 東京本社編集局産業部長
1998年 出版局長
2001年 テレビ東京常務取締役
2004年 BSテレビ東京代表取締役社長
2007年 テレビ大阪代表取締役社長
2010年 同 代表取締役会長
現在、東通産業社外取締役、日本記者クラブ会員
趣味は美術鑑賞

第13回 『「石油」の終わり。怖いのは「オイル(油)より老いる・ショック」~「産業の興亡・企業の盛衰」Part2』