第24回『「プーチン・ショック」の「エネルギー危機」をどう乗り切るか(産業の興亡・企業の盛衰〜Part4)』
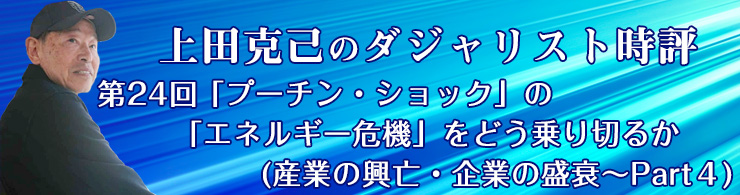
「プーチン・ショック」の「エネルギー危機」をどう乗り切るか(産業の興亡・企業の盛衰〜Part4)
参議院選挙は自民党が圧勝した。投票日の2日前に安倍晋三元首相が凶弾に倒れる変事があり、有権者の投票行動に影響した可能性が高い。これで岸田政権は少なくとも3年間は衆参両院で過半数を握り、安定した政権運営が出来る。課題は山積しているが、最優先の重要課題の一つは「エネルギー危機」対策だろう。
ウクライナ戦争の勃発に加え円安で、ガソリンなどの石油製品、電気・ガス料金などが大幅に上昇している。電気は「供給力不足で停電」の懸念も強まっている。
第2次大戦後、日本が「エネルギー危機」に直面するのは3度目。第1次の危機は1973年のOPECによる大幅な原油価格引き上げによる「オイル・ショック」。第2次は2011年の東日本大震災で発生した福島原発事故により原子力発電所が全て停止した「アトミック・ショック」。そして第3次の危機はロシアのウクライナ侵攻に対する経済制裁でロシア産の石油、天然ガスの供給が大幅に減少した「プーチン・ショック」である。
第1次の「オイル・ショック」で日本が目指したのは「脱・石油、脱・中東」で、石油に替わって力を入れたのは「原子力発電」。つまり「脱油入原」である。
ところが、第2次の「アトミック・ショック」で、エネルギー源のベースとした原発の稼働、新増設が難しくなった。気候変動対策の必要性も高まり、原発に替わって太陽光発電などの「再生可能エネルギー」の開発、増強が急務となって来た。「脱原入再(エネ)」への転換である。
第3次の「プーチン・ショック」では日本もEUと共にエネルギー資源の「ロシア依存からの脱却」を迫られている。そして気候変動対策として引き続き「脱炭素」の推進とエネルギーの「自給率の向上、国産エネルギーの開発」が改めて課題となって来た。つまり「脱露入国」なのだ。
過去2度のエネルギー危機に対して日本が採った「エネルギー転換政策」は、結局「実現出来なかった」か、「結果的に失敗」だった。それが「日本産業の競争力の低下、日本経済の衰退」の一因ともなっている。今回の危機は「3度目の正直」。もう「政策の失敗」は許されない。なぜ「日本のエネルギー政策は失敗して来たのか」を点検し、「3度目の正直とすべき政策」を考えたい。
1980年代までの「石油の時代」はサウジアラビアを中心とした中東原油が安く、豊富だった。中東の政治情勢が不安定でも「石油の調達源の多様化」は経済面から得策ではなかった。だから日本が「原発の増強」に舵を切ったのは、当時としては理解できる。
ただ日本列島は地層が複雑、地盤が弱く、火山が多く、地震の多発地帯。原発の「適正な立地」は極めて少ない。にも関わらず原発の建設主体は地域独占の9電力会社で、各社が独自に原発の建設、保有を競った。その結果、原発立地に相応しくない地域にも原発が建設された。そうした実態を「政・官・学・財」で構成した「原子力村」は「安全神話」を創作し、覆い隠して来た。
「アトミック・ショック」で「神話」は消え、「無理な立地の実態」が露呈した。福島原発事故は不適正な立地にも関わらず、安全神話に染まった東電などの「危機意識の弛緩」が招いた結果だろう。「アトミック・ショック」では原発の稼働停止で一部電力会社に電力不足が生じ、「計画停電」を余儀なくされた。そこで様々な対策が叫ばれたが、中でも各電力会社間で電力を融通する「連系線の増強」が強く指摘された。
しかし、日経新聞によると「東西を結ぶ送電線の弱さは10年以上を経ても解消されていない」。原発に代わる脱炭素電源として「再生エネの普及拡大」も最重点対策に取り上げられた。再生エネは天候などに左右され、発電量が不安定で、電力の需給調整が必要となる。需給バランスが崩れると、大規模停電に繋がる恐れがある。ところが需給調整に必要な「蓄電」や「送配電網」の拡充も「未だ極めて不十分」(日経)だ。
未曾有の原発事故を起こし、深刻な「電力不足・停電」を経験したにも関わらず、経産省と旧地域独占の9電力の「対策は手緩い」と感じるのは「何故か」。「電力需給を逼迫させ、休止原発の再稼働を早めよう」との「魂胆ではないか」と勘繰りたくなる。
案の定、参院選に圧勝した岸田首相は「(今冬懸念の)電力需給の逼迫」対策として早速「原発5基の再稼働」方針を打ち出した。現在稼働中の原発は4基なので、今秋には稼働原発は一挙に倍増しそうだ。「3度目の正直」のはずの「エネルギー危機対策」が「原発再稼働の促進」では、また「いつか来た道」ではないか。これでは、今度こそ本当に「取り返しのつかない危機に直面しかねない」と心配だ。
東京電力は嘗ては「世界一の電力会社」だった。それが原発事故によって巨額の補償、廃炉などの費用負担を抱え込む羽目となった。このため事実上、国有化されたが、更に「チッソ化」の道を辿るのではないか、と懸念される。「チッソ化」とは「水俣病の補償支払い会社として存続しているチッソ」のような存在。
これ程の苛酷な状況に至りながら、9電力会社が原発再稼働に固執するのは何故か。当面の電力不足に対応するには「既存設備の活用しかなく、原発は脱炭素で経済的」が9電力の主張のようだ。
しかし、未だに使用済み核燃料の最終処理場のメドも全く着かない原発のトータルコストは算定出来ない。中長期で見れば再エネのコスト優位は明らか。それでも9電力はこれまで「原発に注力し、再エネに消極的」だった。それは電力自由化の潮流下、「電源設備を原発中心に大規模集中化することで発電事業への参入障壁を高くする狙いだった」と見るのは穿ち過ぎだろうか。
3次に渡るエネルギー危機の教訓は「原燃料の外部依存は国際政治に左右され不安定」「原発のような大規模電源への集中は災害などリスクが高い」。従って「理想のエネルギー」は「原燃料は国産の脱炭素エネで、電源は多様で地方分散、小規模でも経済性がある再エネ」ではないだろうか。
スローガン的に表現すれば「国産エネルギーで自給率向上」「エネルギーの地産地消でコストダウンと地方活性化」である。そのためには太陽光、風力、水力、潮力、地熱、バイオなどあらゆる再エネを活用して行かねばならない。
そんな構図は「夢物語、経済性がない」と一蹴する向きが多いだろう。しかし、「エネルギーと食糧の高い自給率」こそ「経済安全保障」の2大要諦で、政策の究極目標だ。その「理想に向かって進むのが政治」であり、エネルギー事業に携わる「公益事業者の使命」ではないだろうか。
2016年4月の電力小売り完全自由化で「新電力」会社が700社以上も誕生した。それが「プーチン・ショック」と円安による仕入れ電力の値上がりで、倒産、転廃業が6月初めで100社以上に達した。ある程度の淘汰はやむを得ないが、顧客が新たな電力会社と契約できず「電力難民」が発生しかねない状況は肝心の「自由化」にブレーキをかける。そうなれば「エネルギーの安定・低廉供給」というエネルギー政策の根本目標に背き、「政策の失敗」となる。
もう一つ避けなければならないのは9電力系列の送配電会社が「太陽光発電の電力受け入れを抑制したり、拒否する動き」。天候に左右される太陽光などの再エネは需給調整が難しいのが理由だ。9電力の直面する状況は理解できるが、日本は「3度目の危機」に至っては、ドイツを見習い「原発に見切りをつけ、再エネを電力増強の最優先にすべき」だろう。
日本は再エネについては「太陽光は平野が少ない、風力は遠浅の海岸が乏しい」など不利な条件が挙げられるが、太陽光パネルの設置は平地ばかりではない。東京都は「新築戸建て住宅に太陽光パネルの設置を義務付ける」方針。鉄鋼・化学の重化学コンビナートが老朽化、スクラップ後の再利用が課題となっている。2400以上もあるゴルフ場もメガソーラへの転用が、可能だ。降雨量の多い日本の「水力の再開発」「豊富な地熱の活用」など未開の余地は多い。
日本に「適地がないのは原発立地で、再エネ立地の適地は何処でも、いくらでもある」。ただ地方分散、小規模の再エネ設備を効率運用するには電力システムの再構築が必要で、時間とカネがかかり、技術革新も求められる。だから国を挙げて一刻も早く「再エネ増強、エネルギーの国産化に取り組まなければならない」。
需要サイドでも脱炭素の流れで、自動車のEV化が急速に進んでいる。再エネ増強とEV化の進展は相乗効果を産むとの期待もある。
日本の「再エネ増強・国産エネルギーの自給率向上」が進めば、これまでの「エネルギー危機」で課題となり、達成できなかった「脱中東、脱石油、脱原発 」は一挙に解決できる。それは「資源を持たざる国」日本が宿命と思われた「エネルギー危機」からの「解放」を意味する。しかも「脱炭素による脱エネルギー危機」である。日本にとってエネルギー政策の「最終目標の達成」であり、「究極のエネルギー転換」である。
2022・7・19
上田 克己
プロフィール
上田 克己(うえだ・かつみ)
1944年 福岡県豊前市出身
1968年 慶応義塾大学卒業 同年 日本経済新聞社入社
1983年 ロンドン特派員
1991年 東京本社編集局産業部長
1998年 出版局長
2001年 テレビ東京常務取締役
2004年 BSテレビ東京代表取締役社長
2007年 テレビ大阪代表取締役社長
2010年 同 代表取締役会長
現在、東通産業社外取締役、日本記者クラブ会員
趣味は美術鑑賞

第23回『北朝鮮のミサイル乱射で波高し日本海〜コロナ禍とウクライナ戦争で「日本海時代」の再来も』