第40回『日本のリスク〜我々は何にどう備えるべきか』
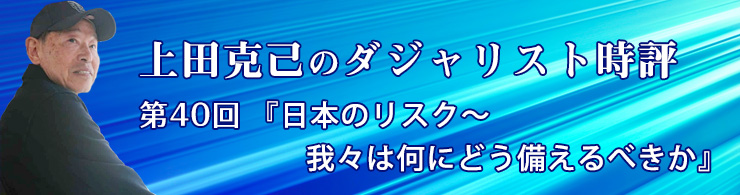
日本のリスク〜我々は何にどう備えるべきか
2025年は「昭和 100年」に当たる。太平洋戦争敗戦からの「戦後80年」、日韓国交正常化60年、阪神淡路大震災30年など様々な周年を迎え、歴史的に「節目の年」である。そこで我々が生きて来た時代の「災禍・危機」を振り返り、現代の「日本のリスク」を確認し、「デリスキング(リスク軽減)」に備えたい。
「昭和100年」の最大の災禍は「戦争」である。昭和16年(1941年)12月8日に始まった「太平洋戦争」で3年8ヶ月の間に日本人の死者は約310万人、日本本土への空襲は215都市、全半焼家屋は約245万戸に上った。そして人類史上初の原子爆弾の投下に2発も見舞われた。
日本は、その歴史上嘗て無い「無条件降伏の敗戦」で「国家存亡の危機」に直面した。この「災い」の余りの大きさに「懲り」て、占領軍司令部のGHQの指示に従い「戦争放棄の平和憲法」を制定。そして米国と「安全保障条約」を結び、「80年間の平和」を享受して来た。
戦死者の数では日本を遥かに上回ったのがソ連。戦勝国だが、第2次大戦の戦死者は約2700万人と突出している。大部分が「ヒットラーのドイツ」との戦いの果てだが、敗戦国のドイツの戦死者は日本とほぼ等しい約300万人超。ソ連に戦死者がケタ違いに多いのは、兵だけでなく、市民をも撤退・疎開を許さない「人間を盾」にした人海戦術が招いた結果と見られる。
これほどの犠牲を出しながらソ連、その継承国のロシアは第2次大戦後も「懲りず」にアフガニスタンなどを侵略、他国の紛争へ介入、「戦争」を繰り返して来た。そして現在、ロシアの侵略で始まった「ウクライナ戦争」は4年目に入っている。
ウクライナ戦でもロシア軍は敵地で交戦していなが死者数は英国防省によると、この3月中旬までで20万人から25万人にのぼる。これはウクライナ軍の5倍強に当たる。「1人の死は悲劇だが、10万人の死は統計」とのチャーチルの指摘をプーチンは実感しているのだろうか。
欧州のど真ん中で行われているウクライナ戦争の「帰趨」が欧州のみならず、世界の21世紀前半の「地政学的リスク」を規定しそうだ。その鍵を握るのは「侵略国」のロシアのプーチン大統領とウクライナの「最大の後ろ盾」である米国のトランプ大統領。当面、世界はこの2人の「大国のリーダー」の言動・交渉に注視せざるを得ない。
ところが予てよりトランプはプーチンと「敵対」するのではなく、その能力を評価、「信頼関係」を匂わせて来た。なぜトランプが日本を含め西側諸国が支援して来たウクライナのゼレンスキー大統領よりも「プーチン寄りの姿勢」を示すのか。この「謎」を解くのが西側諸国の「喫緊の課題」である。以下はダジャリストの「独断」の一考察である。
トランプは大統領就任の1期目から「『陰謀論』に染まっている」とダジャリストは感じて来た。だからダジャリストは陰謀論にハマらず、鋭い「風刺」を目指しているが、対象が「不動産屋のトランプと元スパイのプーチン」だと「陰謀論まがい」のレトリックに陥りそうになる。
米国大統領でありながらトランプの言動が終始「プーチン寄り」になるのはトランプがプーチンに「『弱み』を握られている」のと「『借り』がある」からではないだろうか。「弱み」は予て噂さされて来た「トランプはモスクワで『ハニートラップ』にかかり、その行状をプーチンに握られている『疑惑』」である。
トランプが初めてロシアを訪れたのは1987年。以来度々、モスクワを訪問、クレムリン宮殿の向かいにトランプ・タワーの建設を計画、2013年にはモスクワでミス・ユニバースのコンテストを主催、司会するなど派手に行動した。その挙句にトランプはプーチンが所属したKGBが得意とする工作活動の「ハニートラップ」にまんまとハマった。
トランプには艶聞が絶えない。米国内でも「ポルノ女優との不倫口止め料」事件で有罪判決が出た。2度の離婚もトランプの浮気が原因。トランプはプーチンの「格好の餌食」となったようだ。「借り」はトランプがヒラリー・クリントンを破った2016年の大統領選での「ロシアゲート疑惑」。トランプ陣営は「ロシアと共謀」、ロシアがクリントン陣営へサイバー攻撃などを仕掛け、クリントンのイメージダウンを工作し、選挙戦を勝利した。
この「疑惑」をトランプは否定、「米国政治史上、最大の魔女狩り」と反発して来た。ところが、「トランプ2・0」が実現すると、トランプは「プーチンとの関係」について「ロシア疑惑を一緒に乗り越えて来た」と言って憚らない。その両氏の関係に「友情」を感じているトランプ側近もいる。両氏とG8サミットで議論を交わしたドイツのメルケルは「トランプはプーチンに魅了されていた」と回想録に綴っている。
こうした「関係」に加え、トランプとプーチンが「親密」なのは、意識・価値観・体質などに「共通点」があるからではないだろうか。
その1つは西欧首脳への「コンプレックスと反感」。
日本が1975年から参加した先進国首脳会議(G5サミット)にソ連(ロシア)が参加し、「G8」となったのは1998年で、ロシアは最も新参メンバー。プーチンは2000年から参加したが、西側の民主・自由主義国家の首脳に囲まれて居心地がいいはずはない。2008年にメドベージェフへ大統領の座を譲り、サミット出席も5回外れ、2013年 の英国北アイルランドのロック・アーンのサミットへ6年ぶりに復帰した。
しかし、ロック・アーンでは政府や企業の「データの透明性(オープンデータ)」やロシアが介入していた「シリア紛争」などが主要議題となり、プーチンは肩身の狭い思いをしたようだ。英国貴族のキャメロンを始めサミット参加国の首脳に対し「私は元KGBの邪悪な男。皆さんは育ちが良く、立派な教育を受けている。私は皆さんほど民主的でないと思われても反論しません」と自虐的な発言をした、と伝えられている。これが事実ならプーチンの「西側首脳へのコンプレックスと反感」は疑いなく、根が深い。
翌2014年に、プーチンはウクライナ領のクリミア半島を一方的に併合する暴挙に出た。その結果、ロシアは「G8サミット」から排除された。プーチンの西側諸国に対する「反発・怒り」は増幅し、「ウクライナ侵攻」へと向かったのではないだろうか。
トランプのG7サミットへの初参加は2017年。翌年のカナダ・シャルルボワのサミットでメルケルがトランプを詰問、それを他のG7首脳が取り囲む写真が流れ、「米国とEUとの対立」を世界に印象付けた。発端はトランプの鉄鋼・アルミの輸入関税引き上げに対する抗議だった。これに「懲りず」にトランプは2期目も「関税カード」を振りかざしG7首脳に総スカンを食っている。
元々、トランプはメルケルやマクロンなどEUの「高学歴インテリ政治家」と肌が合わない。EUのような多国間同盟を嫌い、NATOや国連も軽視している。こうした点もプーチンと共通している。この両氏でウクライナ戦争の「手打ち」をしようとすれば、ウクライナは浮かばれず、「欧州の危機」は深まるばかりだろう。
更にプーチンは「ソ連邦の崩壊は20世紀最大の地政学的惨事」と悔み、その「復活の野望」を隠さない。トランプは「カナダの併合、パナマ運河の奪還、グリーランドの領有」などを臆面もなく主張、「MAGA(米国を再び偉大に)」をスローガンに掲げる。いずれも「時代錯誤なアナクロニスト」に唖然とするばかりだ。
実はこの両氏に加えてもう1つの大国のリーダー、中国の習近平総書記も似た体質・意識の持ち主だ。2012年に共産党総書記に就任以来、「中華民族の偉大なる復興」を目指す「中国の夢」をスローガンに内は毛沢東ばりの「思想教育」を強化、外は「一帯一路」の拡大戦略を推進している。そして総書記の任期をプーチンと同様、延長、「長期独裁政権」へ突き進んでいる。
米ソの「冷戦の終結」で世界は「パクス・アメリカーナ(アメリカによる平和)」が確立、永続するかと思われた。ところが、米国の「国力低下」が進行、そこへ知性・品性を欠くトランプの再登場で「威信失墜」が重なり「米国の世紀」は終焉を迎えている。世界は多極化し、「パクス・コンソルテイス(連合による平和)」へ向かわざる得ないのではないだろうか。
ただ当面は、ロシア、米国、中国の「3大国の影響力」が大きい。そのリーダーの「プーチン(Putin)、トランプ(Trump)、習近平(Xi Jinping)」の「政策・方針の如何」に世界情勢は左右される。つまり「PTX」次第なのだ。辞書を引くと「PTXはパクリタキセルの略称」で肺がんなどの有効な治療薬。
人類社会の最大の「悪」であり、「がん」は「戦争」である。「昭和100年」を振り返って日本そして世界の「最大の災い」は「第2次大戦(太平洋戦争)」だった。それにも関わらず、その戦場となった地域で今も「懲りず」に戦争が行われている。「人間の愚かさ」を自虐するばかりだ。世界の大国のリーダー「PTX」は「大戦後80年」経っても発症し転移する「戦争という『がん』」を早急に退治する責務がある。
しかし、3リーダーの「PTX」がその効力を持っているか、残念ながら甚だ疑わしい。この現実こそ日本そして世界が今、直面している「最大のリスク」ではないだろうか。
世界は、こうしたリーダーを抱えた「大国の時代」を早く脱しなければならない。そして「自由と民主主義」を尊重し、「人間性」豊かなリーダーが政治・経済の舵取りをする「小国の連合」が活躍する「パクス・コンソルテイス」を目指すべきだ。
次は「戦後80年」と「阪神淡路大震災30年」を振り返えり、石油ショックなどの「人災」や地震などの「天災」のリスクに「どう対応するか」を考えたい。(敬称略)
2025・3・26
上田克己
プロフィール
上田 克己(うえだ・かつみ)
1944年 福岡県豊前市出身
1968年 慶応義塾大学卒業 同年 日本経済新聞社入社
1983年 ロンドン特派員
1991年 東京本社編集局産業部長
1998年 出版局長
2001年 テレビ東京常務取締役
2004年 BSテレビ東京代表取締役社長
2007年 テレビ大阪代表取締役社長
2010年 同 代表取締役会長
現在、東通産業社外取締役、日本記者クラブ会員
趣味は美術鑑賞

第39回[続々]『2024世界選挙イヤー~試される民主主義』