スマホやAIが医療を変える

スマートホンやAIなど新しい情報技術(ICT)を医療に導入して医療が抱える問題を解決しようとうする動きが活発化しています。一方で、技術の進歩に追いつかない種々の規制や開発投資を回収する仕組みなどに多くの課題も指摘されています。種々のアプリも開発で実績を上げてきた東京慈恵会医科大学の高尾准教授は、最終的には患者さんにどのような利益を提供できるどうかがICT医療成否の鍵を握ると指摘しています。
スマホの普及やクラウド、AI(人工知能)などの情報コミュニケーション技術(ICT)の発達によって、医療が変わろうとしています。それは医師や看護師の働き方や診断・治療法を変えることにとどまらず、病気にならず健康的に暮らしたいとすべての人々の願いをかなえる可能性があります。
アプリ単独で保険診療の適用に
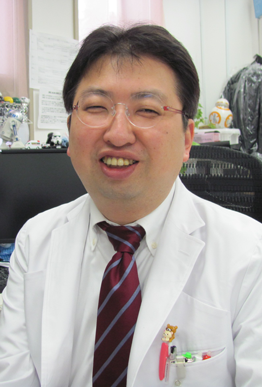
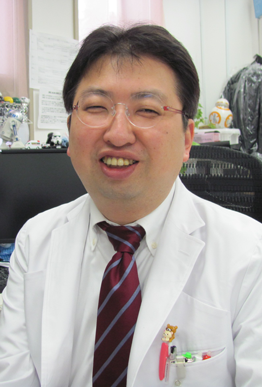
以前は医療用ソフトというと、医療機器に付属していました。しかし最近、環境は大きく変わりつつあります。その一例が規制の変化です。日本では2014年11月に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」という新しい法律ができました。その結果、医療用ソフトウエア単体で医療機器と認められるようになり、アプリを医療現場に導入しやすくなりました。これによって専用の医療機器を持たないアプリも医療機器として認められ、医療行為に使用できるようになりました。
私が勤務する東京慈恵会医科大学(慈恵医大)と医療ソフト会社のアルム(東京都渋谷区)は共同で、モバイルで使える医療関係者間コミュニケーションアプリ「Join」を開発しました。平成28年(2016年)4月1日より保険診療の適用が開始されています。これは汎用画像診断装置用プログラムの性格を持ったソフトで、救急現場で「専門医が院内にいないが、でもすぐに情報がほしい」という事態になったときに、モバイルとクラウドによって医療関係者間のコミュニケーションを取ることができます。医療用画像管理システム(PACS)とも連携し、必要な医療情報を医療関係者の間で迅速に共有することが可能です。慈恵医大では既に400人の医療スタッフが日常的に使用しています。
このJoinの導入によって脳梗塞の患者さんに血栓溶解酵素製剤の組織プラスミノーゲーンアクチベータ(t-PA)を施行するまでの時間を30分ほど短縮できるという研究結果をまとめました。脳梗塞の治療では発症後、できる限り早く治療を開始する必要があります。発症後からt-PAの投与開始が短ければ短いほど、救命率も高くなるとする多くの研究もあります。したがってJoinの導入は脳梗塞の救命率を上げる可能性があります。研究の詳細は、近く論文として発表したいと考えています。
バラバラだった情報を統合する
医療用ICTの最も重要な用途というと、まっさきに挙げたいのが“パーソナルヘルスレコード”(PHR)です。これまでの個人の医療情報(検査結果、治療歴など)は治療を受けた病院ごとにバラバラに保管されてきました。PHRはこうした医療情報を1つにまとめることをコンセプトにしています。患者が過去に風疹にかかったことがあるのか、薬のアレルギーはあるか、既往症はあるのかなどが一元管理できれば、検査の重複を避けたり、患者の個人的な体質に起因する医療過誤を回避したりしやすくなります。
さらに、患者の同意のもと、得られた臨床データをクラウドに蓄積し、適切に個人を特定出来ないように匿名化して医療研究に利用することも可能になります。PHR利用が日常的になれば、患者さん自身にとって自分の医療情報・健康情報が身近になり、健康に対する意識も自然と高まるはずです。
個人の医療情報はだれのものか
PHRシステムの開発については厚生労働省もかなり力を入れ始めていますが、日本だけではなく世界中で利用が始まっています。様々なメリットが想定される一方で課題もあります。とりわけ重要なのが、プライバシーへの配慮です。PHRが扱う情報は最も重要な個人情報の一つには違いなく、慎重に考える必要があります。
病院に保管している患者のカルテなど個人の医療情報は患者本人のものです。PHRの実現には、個人が自分の医療情報の持ち主だと考え、一人ひとりが情報の提供先をしっかりコントロールしていく必要があるでしょう。
現在でも重度の糖尿病を患っている人の中には民間保険への加入が制限される例もあります。しかし、一律に保険に加入できないとするのではなく、スマホのPHRで糖尿病の重症化の指標であるHbA1c値が下がったなど、病気が改善していることを記録しデータの活用をすれば保険の加入できるようにすることも考えられます。
現在の生命保険会社の業務は保険料の徴収と保険金の給付が中心ですが、今後はPHRを利用した様々なサービスを提供することによって、被保険者の健康を維持し、結果的に保険金の給付を減らして利益を上げるという新しいビジネスモデルの構築も期待できるでしょう。このようなPHRのデータを企業と共有して新しい事業を展開する「情報銀行」という概念も積極的に提案していきたいと思います。
ウエアラブル・デバイスの活用
慈恵医大では医工連携により、患者が身につけるウエアラブルデバイスの開発にも取り組んでいます。現在、リストバンド型の機器の開発中です。これは、計測した血圧や脈拍のデータを病院などの医療機関とやりとりできるシステムの入力装置ですが、着用者の様態が急変した際には、駆け付けた救急隊が容体を確認し、その問診データをクラウドに送信すると、AIがこれまでの症例を参考に着用者の状態を分析します。救急隊はその分析を参考に搬送先を選択するなど、最適な処置法を選ぶことができます。
さらに慈恵医大ではメガネ型のウエラブルデバイスも開発しています。まばたきや眼球運動、瞳孔の縮小や拡大といった眼の動きを計測し、うつ病や認知症など精神疾患の診断や経過観察に役立てることを目的にしています。リストバンドと同様のシステムで着用者の状態を継続的に評価し、重症化を予防するケアにつなげていきたいと思います。
ICTを利用して健全な長寿国家を
ICTを適切に利用することができれば、日本は長寿国家であり続けることができます。医療環境が良い国は仕事ができる人口が多くなり、発展していくはずです。電話が携帯電話になり、スマホに変わったように、医療も新しい形に変化していくはずです。そのためにはICTを利用して世の中の流れを変えて行く仕組みが大切です。そして最終的にはそれが患者さんに多くの利益をもたらすものになることが最も重要です。
高尾洋之(たかお・ひろゆき)先生
2001年東京慈恵医科大学卒業、10年に同大学臨床大学院博士課程修了(脳神経外科学講座)。12年カリフォルニア大学ロサンゼルス校神経放射線科留学。14年厚生労働省医政局研究開発振興課医療技術情報推進室室長補佐。14年に同経済課課長補佐。15年から東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科学講座/先端医療情報技術研究講座(兼任)准教授。
